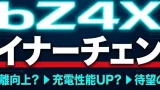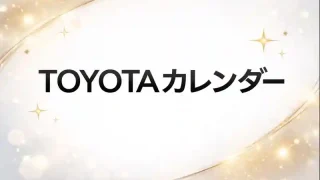「bZ4Xが売れない」という声が、自動車業界や消費者の間で囁かれています。鳴り物入りで登場したトヨタ初の量産EVでありながら、その売れ行きは、特に日本国内で苦戦を強いられているのが現状です。なぜ、これほどまでに注目されたモデルが、市場の期待に応えられていないのでしょうか。一部では「価格が高すぎる」との指摘もありますが、理由はそれだけではないようです。
この記事では、bZ4Xが抱える課題を多角的に分析し、その背景にある根本的な原因を深掘りしていきます。
この記事を読めば、以下の5つのことがわかります。
- bZ4Xの国内における具体的な販売状況
- ライバル車と比較して「高すぎる」と言われる価格設定の実態
- 販売戦略やサブスクリプションモデルが与えた影響
- リコール問題がブランドイメージに及ぼしたダメージ
- 今後のトヨタのEV戦略とbZ4Xの将来性
bZ4Xは売れない?日本のBEV売上ランキング
トヨタ初の本格BEV(電気自動車)として登場したbZ4Xの販売台数は、2024年通年約1000台、2025年1-6月で約200台程度と残念ながら好調とは言えない状況です 。この背景には、軽EVである日産「サクラ」が国産BEV全体の半分を優に占めるという圧倒的な強さで市場を牽引していること、そして乗用車タイプのBEVでは輸入車の存在感が非常に大きいという、日本のBEV市場ならではの特殊な構造があります 。
bZ4Xがどのような立ち位置にいるのか、まずは日本のBEV販売ランキングから見ていきましょう。
▼2025年上半期・国産BEV販売ランキング(推定)
| 順位 | 車種名 | 販売比率 | 特徴 |
| 1位 | 日産 サクラ | 60%超 | 軽EVとして圧倒的な人気。日本のBEV市場を牽引。 |
| 2位 | 日産 リーフ | 15% 前後 |
モデル末期ながらも根強い需要を誇るBEVのパイオニア。 |
| 3位 | 日産 アリア | 約5%強 | 中型SUVタイプのBEV。 |
| 3or4位? | 三菱 eKクロスEV | 約5%強 | サクラと兄弟車。軽EVのもう一つの人気モデル。 |
| 5~8位 | トヨタ bZ4X | ?? | 販売台数は横ばいで推移。 |
| 5~8 位 |
レクサス RZ | ?? | bZ4Xとプラットフォームを共有するレクサスブランドのBEV。 |
| 5~8 位 |
マツダ MX-30 EV | ?? | ユニークなデザインが特徴。 |
| 5~8 位 |
スバル ソルテラ | ?? | bZ4Xの兄弟車。 |
BEVの販売台数は、サクラとリーフだけで8割近くを占めています。とくに日産サクラは、2024年度に年間2万台以上を販売し、3年連続で国内EV販売台数No.1の座を獲得しています 。
そして、もう一つ重要なポイントが、このランキングは「国産車」に限定されている点です。2025年8月時点のデータでは、軽自動車を除いた「登録車BEV」の約90%がテスラや中国、ヨーロッパなどの輸入車で占められています 。つまり、bZ4Xが戦っている土俵は、強力な輸入車勢がひしめく厳しい市場なのです。
▼ランキングから見えてくる「日本の現実」
このデータは、単にbZ4Xが売れていないという事実以上に、日本のユーザーがBEVに何を求めているかを浮き彫りにしています。多くの人々は、高価で大きなBEVよりも、日常の足として気軽に使える「軽EV」を現実的な選択肢として捉えているようです。また、新しいもの好きや性能を重視する層は、早くから市場に参入していた輸入車ブランドに流れている、という構図も見えてきますね。
▼データを見る上でのちょっとしたヒント
EVの販売台数は、補助金の切り替わりや年度末の登録などが影響し、月によって大きく変動することがあります 。そのため、一つの月のデータだけで判断するのではなく、長いスパンで見るのが推奨されます。
なぜ日本でbZ4Xは売れないか:3つの理由
bZ4Xが日本市場で販売に苦戦している理由は、単にクルマの性能が悪いから、という単純な話ではありません。主に「①価格帯と日本のBEV需要とのミスマッチ」「②発売当初の販売方法と品質トラブルの影響」「③日本の充電インフラを取り巻く市場環境」という3つの要因が、複雑に絡み合っていると考えられます。
▼理由①:価格と需要のミスマッチ
bZ4Xの価格は550万円〜650万円 。これは、日本のBEV市場で最も売れている日産サクラ(約260万〜310万円)の倍近い価格帯です。日本のBEV市場は「日常使いの手頃な軽EV」が中心であり、bZ4XのようなミドルサイズSUVのBEVに対する需要層がまだ薄いのが現状です 。
さらに、同じ価格帯には性能や先進性で評価の高いテスラやヒョンデ、BYDといった輸入車が強力なライバルとして存在します 。ユーザーからは静粛性や乗り心地を評価する声がある一方で、「補助金を使っても、他のBEVやPHEV(プラグインハイブリッド)と比べると割高に感じる」という意見も少なくありません。
▼理由②:初期戦略の“長い影”
bZ4Xは2022年5月の国内導入時、サブスクリプションサービス「KINTO」でのリース契約専門という、特殊な販売方法でスタートしました 。「現金で買えない」「将来の資産価値が不安」といった声が多く、購入を検討していた層を取りこぼしてしまった可能性があります。
その後、2023年11月から一般販売も開始されましたが、一度ついた「買いにくいクルマ」というイメージは簡単には払拭できません。さらに、発売直後にタイヤのハブボルトに関するリコールで生産・販売が長期間停止したことも、ブランドイメージに少なからず影響を与えました 。
▼理由③:日本の市場環境という逆風
日本の新車販売全体に占めるBEVの割合(シェア)は、まだ2〜3%程度で伸び悩んでいます 。つまり、BEV市場そのものがまだ小さいのです。
また、懸念されるのが充電インフラの問題です。充電器の数は増えているものの、特に長距離移動の要となる「高出力の急速充電器」はまだ十分とは言えません。bZ4Xは90kWの急速充電器を使っても80%まで約40分かかるとされていますが 、高速道路のサービスエリアなどでは30分という時間制限がある場合も多く、「思ったように充電できない」というストレスを感じる可能性があります。近距離移動がメインの軽EVと比べ、長距離移動もこなすSUVだからこそ、このインフラ問題がよりクリティカルな弱点となってしまうのです。
▼もし発売当初にタイムスリップできるなら…
もし筆者が当時のトヨタの担当者だったら…と考えると、やはり「最初から一般販売も並行して行う」という選択をしたかったですね。BEVのような新しいカテゴリーのクルマこそ、多様な買い方を提供し、一人でも多くの人に触れてもらう機会を作ることが重要だったのではないでしょうか。初期の戦略が、bZ4Xのポテンシャルを十分に発揮する上での大きな足かせになってしまったように感じられて、少しもったいない気がします。
▼ユーザー体験が未来を創る
結局のところ、クルマが売れるかどうかは「買ってよかった」というポジティブな体験談がどれだけ広がるかにかかっています。bZ4Xもクルマ自体の乗り味は評価が高いだけに、価格や充電環境といった「体験」の部分でマイナスイメージが先行してしまったのが現状です。今後、これらの課題を一つずつ解消していくことが、再評価への道筋となりそうです。
日本のBEV普及率ってどれぐらい?
日本のBEV普及率は、2024年の新車販売台数に占める割合(販売シェア)が約1.5%程度、国内を走るクルマ全体に占める割合も2%弱と、世界の主要国(10%~80%)と比較すると、かなり低い水準にあるのが実情です 。ただし、ハイブリッド車(HV)を含めた「電動車」という広い括りで見ると普及は進んでおり、この「BEV」と「電動車」の言葉の違いを理解することが、現状を正しく把握するカギとなります。
▼「販売シェア」と「保有台数シェア」
まず、BEVの普及率を語る上で大切な2つの言葉を整理しましょう。
- 販売シェア:その年に売れた新車全体のうち、BEVが何%を占めるか、という割合です。市場の「今の勢い」を示します。
- 保有台数シェア:日本国内で登録されているクルマ(乗用車)全体のうち、BEVが何%を占めるか、という割合です。これまでの「積み重ね」を示します。
最新のデータを見ても、2025年8月の月次データでBEVの販売シェアは約1.5% 。PHEV(プラグインハイブリッド)を足しても約2.5%と 、新車販売の中でもBEVはまだ少数派であることがわかります。
▼数字の裏にある「ハイブリッド大国ニッポン」
なぜ日本のBEV普及は遅れているのでしょうか。その大きな理由の一つが、ハイブリッド車(HV)が絶大な人気を誇っているからです。月によっては新車販売の半分以上をHVが占めることもあり、「電動車」という大きな括りで見ると、日本の電動化率は決して低くありません 。
多くの日本人にとって、充電の心配がなく、燃費も良いHVは非常に合理的で魅力的な選択肢です。この強力なHVの存在が、BEVへの移行を緩やかにしている側面は否めません。
▼軽EVが支える日本のBEV市場
もう一つの日本の特徴が、BEV販売の半分以上を「軽EV」が占める時期もあるということです 。日産サクラや三菱eKクロスEVのヒットがなければ、日本のBEV販売シェアはさらに低い数字になっていたでしょう。これは、日本の道路事情や生活スタイルに、小型で小回りの利くBEVがマッチしている証拠とも言えます。
▼世界との比較で見える立ち位置
国際エネルギー機関(IEA)の比較データを見ると、日本はEVの保有台数シェアが「2%未満」のグループに明確に位置付けられています 。BEVの普及が80%を超えるノルウェーや、20%を超える中国・ヨーロッパの国々と比べると、日本が周回遅れであることは客観的な事実です。
▼あなたの生活にはどっち?
もしあなたがクルマの買い替えを検討しているなら、「BEVか、ガソリン車か」の二択だけでなく、「ハイブリッド車」という選択肢も有力な候補になるのが日本の面白いところです。毎日長距離を走るならまだHVに分がありますし、近所の買い物や通勤がメインならBEVが非常に快適です。ご自身のカーライフを想像しながら、最適な「電動車」を探すのが賢い選択と言えそうです。
TOYOTAは世界を見ている:bZ4Xは世界で売れてる
bZ4Xは、日本国内では販売に苦戦しているイメージが強いかもしれませんが、世界に目を向けると、欧米市場を中心に年間5万台以上を売り上げる人気モデルへと成長しています 。特にBEV化が急速に進むヨーロッパや、販売戦略のテコ入れが成功したアメリカで着実に支持を広げており、「日本では売れない=世界でも失敗」という単純な話ではないことがわかります。
▼国が変われば評価も変わる!bZ4Xの世界での活躍
bZ4Xのグローバルな販売実績を見てみると、日本との評価の違いに驚かされるかもしれません。
- ヨーロッパ:2024年には推定で約24,465台を販売 。厳しい環境規制を背景にBEV需要が高まる市場で、トヨタのC-SUVセグメントを担う重要な一台となっています。
- アメリカ:2024年に18,570台を販売し、前年からほぼ倍増(+98%)という急成長を遂げました 。リースプランの改善や、ユーザーの不満点だった寒冷地での充電性能を改善するなどのアップデートが功を奏しています。
- 北欧(ノルウェー):特に象徴的なのが、BEV先進国であるノルウェーでの成功です。2025年1月には、新車販売の約96%がBEVという超成熟市場で、bZ4Xが月間の販売台数No.1に輝きました 。これは、BEVが当たり前になった市場で、トヨタブランドの信頼性が改めて評価された結果と言えるでしょう。
- 中国:世界で最も競争が激しいと言われる中国市場でも、価格改定などを経て2024年には約7,000台を販売しています 。
これらの数字を合計すると、bZ4Xは2024年だけで世界で少なくとも5万台規模の販売主要市場合算で推定5万台の販売(米18,570/欧24,465/中約7,167 ほか)を達成しており、日本の年間1,000台弱という数字とは大きな隔たりがあります 。
▼なぜ海外でbZ4Xは受け入れられたのか?
海外でbZ4Xが成功している背景には、それぞれの市場に合わせた戦略があります。
- 追い風となる政策とインフラ:ヨーロッパでは厳しいCO2規制がメーカーにBEVの販売を促し、充電インフラの整備も進んでいます。
- 柔軟な価格・販売戦略:アメリカでは、市場の反応を見ながらリース条件を改善するなど、柔軟な販売戦略が販売増につながりました。
- 「トヨタ」ブランドへの信頼:BEVが当たり前になった北欧のような市場では、新しい技術であっても「トヨタが作るなら安心だ」という長年培ってきたブランドへの信頼が、最終的な決め手となっています。
トヨタはbZ4Xの販売を通じて、世界各国の市場でBEVを売るためのノウハウを蓄積している最中なのです。
▼グローバル戦略の中でのbZ4Xの役割
日本での販売台数だけを見ると心配になるかもしれませんが、bZ4Xはトヨタにとって、来るべき本格的なBEV時代に向けた重要な「先行投資」であり「実験場」でもあると筆者は考えます。世界中で得られたデータやユーザーからのフィードバックは、間違いなく今後登場するであろう次世代BEVの開発に活かされていくはずです。bZ4Xは、そのための礎を築くという大きな役割を担っているのです。
▼日本のbZ4Xも進化する?
海外では、航続距離の改善や新しいグレードの追加など、年々商品力の向上が図られています 。こうした海外での改良点が、今後「逆輸入」という形で日本仕様にも反映される可能性は十分に考えられます。グローバルで揉まれ、たくましく成長したbZ4Xが、いつか日本市場でも再評価される日が来るかもしれませんね。
BEVが売れている国とその3つの理由
世界には、新車販売の半分以上がBEVという国も珍しくありません。特にノルウェー(2024年BEVシェア88%)を筆頭とする北欧諸国や、デンマーク(同51.5%)、そして巨大市場である中国(同27.6%)などがBEV普及をリードしています 。これらの国々でBEVが急速に普及した背景には、「①強力な購入支援策や税金の優遇」「②フリート(社用車)需要の牽引」「③使いやすい充電インフラの整備」という、3つの共通した理由が存在します。
▼世界のBEV普及率ランキング(2024年実績)
| 国・地域 | BEV販売シェア(目安) | 特徴 |
| ノルウェー | 88% | ほぼBEVへの移行が完了。税制優遇が強力。 |
| デンマーク | 51.5% | 新車の半分以上がBEVに。 |
| スウェーデン | 35% | 企業向け需要が市場を支える。 |
| オランダ | 34.9% | 社用車への優遇策が効果を発揮。 |
| 中国 | 27.6% (小売) | 世界最大のBEV市場。価格競争も激化。 |
| イギリス | 19.6% | ヨーロッパ最大のBEV市場に。フリート需要が牽引。 |
| EU全体 | 13.6% | 地域全体でBEVへのシフトが進む。 |
| アメリカ | 約8〜11% | 地域差が大きい。西海岸などで普及が進む。 |
| 日本 | 約1.4〜1.8% | 主要国の中では低い水準。 |
▼理由①:政策による強力な後押し
BEVが売れている国の最も大きな共通点は、政府による手厚いインセンティブです。例えばノルウェーでは、BEVを購入すると消費税(VAT)や高額な自動車登録税が免除されます。これにより、BEVがガソリン車よりも安く購入できるという「価格の逆転現象」が起きています 。
また、EU全体では厳しいCO2排出量規制があり、達成できないメーカーには罰金が科せられます。そのため、メーカー側も積極的にBEVを販売せざるを得ない状況が生まれているのです。
他にも中国では、政府主導で国内メーカーによる安価高性能なBEVを促し、あっという間に世界最大のBEV大国となりました。
▼理由②:「会社が使うクルマ」から普及が始まる
イギリスやオランダなどで特徴的なのが、フリート(法人向けの社用車やリース車)需要がBEV普及の起爆剤となっている点です 。企業がBEVを導入する際に税制上の優遇があるため、多くの企業が社用車をBEVに切り替えています。
こうして市場に投入されたBEVは、数年後には良質な中古車として個人向け市場に流通します。これにより、個人ユーザーも手頃な価格でBEVを手に入れることができるようになり、普及が一気に加速するという好循環が生まれています。
▼理由③:安心して使える充電インフラ
「遠出した時に充電できるか不安…」というのは、BEVへの乗り換えをためらう大きな理由の一つです。BEV先進国では、高速道路のサービスエリアや主要な拠点に高出力の急速充電器が網の目のように整備されており、この「充電不安」が大幅に解消されています 。
充電器の数だけでなく、決済のスムーズさや稼働状況のリアルタイム確認など、ユーザーがストレスなく使える「使い勝手の良さ」も重視されているのが特徴です。
▼日本がこれから進むべき道は?
これらの成功事例から日本が学べることは多いはずです。単に購入補助金を出すだけでなく、ノルウェーのような思い切った税制優遇や、イギリスのようなフリート需要を刺激する施策、そして誰にとっても使いやすい充電インフラの整備といった、多角的なアプローチが不可欠です。BEV普及は、ユーザーの「欲しい!」という気持ちと、政府やメーカーの「普及させたい!」という強い意志の両輪が揃って、初めて前に進んでいくのかもしれません。
bZ4Xは高すぎる?BEVの相場観—価格相応の実用性はあるか
トヨタ bZ4Xの車両価格は550万円〜650万円。一見すると高価に感じますが、国の補助金を使えば実質的な負担額は460万円前後からとなります。この価格が競合のBEVと比べて高いか安いかは、カタログスペックだけでは見えない「静粛性」や「乗り心地」、そして「トヨタブランドの安心感」といった価値をどう評価するかで、あなたの答えは変わってくるでしょう。
▼bZ4Xの価格と基本性能
まずはbZ4Xの基本情報をおさらいしましょう。
- 価格帯:550万円~650万円
- 航続距離(WLTCモード):540km~567km
- グレードや駆動方式(FF/4WD)、タイヤサイズによって変動します。
- 充電時間(急速充電):約40分で80%まで充電(90kW出力の場合)
- バッテリー保証:10年/20万km(容量70%保証)という手厚い保証
▼補助金を使えば、実質価格はいくら?
BEVの購入時には、国や自治体から補助金が出ます。これが非常に大きいのです。2025年度の国の補助金(CEV補助金)は、たとえば最大90万円になる(年度仕様要件で変化、かならず自治体サイトを確認) 。これだけでも、エントリーグレードのG(FF、550万円)なら実質価格は約460万円になります。
さらに、東京都のように独自の補助金(たとえあ最大100万円:最新の交付要綱/自治体サイトで要確認)を上乗せしてくれる自治体もあり、その場合は実質360万円前後まで下がる可能性も。お住まいの地域の制度を調べてみる価値は十分にありますよ。
▼ライバル車との価格比較
では、bZ4XのライバルとなるミドルサイズSUVのBEVは、いくらぐらいなのでしょうか。
| 車種名 | 価格帯(目安) |
| トヨタ bZ4X | 550万~650万円 |
| テスラ モデルY | 約559万~684万円 |
| ヒョンデ IONIQ 5 | 約524万~614万円 |
| 日産 アリア | 約659万~944万円 |
| BYD SEAL | 約528万~605万円 |
こうして見ると、bZ4Xの価格は競合車種とほぼ同等か、少し高めの価格帯に位置していることがわかります。特に、航続距離や先進装備で評価の高いテスラやヒョンデと比べると、価格的な優位性は小さいかもしれません。
▼価格に見合う価値はどこにある?
bZ4Xの本当の価値は、数字には表れにくい部分にあるのかもしれません。オーナーからは、以下のような声が多く聞かれます。
- 良い点:「とにかく静かで、家族との会話が弾む」「モーターによる加速が滑らかで、運転していて疲れない」「運転支援システムが優秀で安心感がある」
- 気になる点:「シートが体に合わない」「急速充電のスピードがもう少し速ければ…」「車両価格がやはり高い」
特に「静粛性」と「乗り心地の上質さ」は、多くのオーナーが高く評価しているポイントです。試乗してみると、その違いに驚くかもしれません。また、全国に広がるトヨタのディーラー網でサポートを受けられる安心感や、10年20万kmという手厚いバッテリー保証は、輸入車にはない大きな魅力と言えるでしょう。
▼bZ4Xを高すぎると感じるのはサクラの影響も
日本で最も売れているBEVは日産サクラであり、価格帯は倍近くちがう軽EVです。そのため、日本のBEV主要ターゲット層からすれば車2台分の価格になるのがbZ4Xであり、高すぎると思うのも無理はありません。
今後は日本でBEVは普及していくか
結論から言うと、日本のBEV普及は今後、時間はかかりながらも緩やかに進んでいく可能性が高いでしょう。ただし、そのスピードは「①充電インフラ、特に高出力の急速充電器がどれだけ増えるか」「②国産メーカーから手頃な価格帯の魅力的なBEVが登場するか」「③集合住宅など自宅で充電できない層への対策が進むか」という、3つの大きな課題を乗り越えられるかにかかっています。
▼普及を後押しする追い風(ポジティブ要因)
日本のBEV普及には、いくつかの明るい兆しが見えています。
- 政府の明確な目標:政府は「2035年までに新車販売で電動車100%」という目標を掲げています 。(※これはBEVだけでなくHV等も含む目標です)。この目標達成に向け、2030年までに公共の充電器を15万口(うち急速充電は3万口)まで増やす計画も進んでいます 。
- インフラの「質」の向上:NEXCO各社は、2025年度末までに高速道路のSA/PAにある急速充電器を約1,100口へ増やす計画を発表 。単に数を増やすだけでなく、東京駅前に150kW級の充電器が設置されるなど、充電時間を短縮できる「高出力化」も進み始めています。
- 国産メーカーの本気度:トヨタは2026年頃から次世代BEVのラインアップを拡充する計画を発表しており、全固体電池などの革新的な技術開発も進めています 。国内メーカーから魅力的な選択肢が増えれば、市場が活性化することは間違いありません。
- 補助金による購入支援:国や自治体による手厚い購入補助金も、当面は継続される見込みです 。
▼普及を阻む向かい風(ネガティブ要因)
一方で、解決すべき課題も山積みです。
- 根強いユーザーの不安:充電時間、航続距離、そして車両価格の高さに対する消費者の懸念は依然として根強く、BEVの購入意向が伸び悩んでいるという調査結果もあります。
- 集合住宅の充電問題:日本の都市部では集合住宅に住む人が多く、「自宅で充電できない」ことがBEV普及の大きな壁となっています。東京都では新築マンションへの充電器設置を義務化する条例が始まるなど、対策は動き出していますが、全国的な広がりには時間がかかりそうです 。
- 中古車市場の不安定さ:BEVの中古車価格はまだ安定しておらず、「数年後にいくらで売れるのかわからない」というリセールバリューへの不安も、新車購入をためらわせる一因になっています。
▼未来シナリオ:2030年の日本の道路はどうなっている?
これらの要因を踏まえると、いくつかの未来が考えられます。
- ベースシナリオ(最も可能性が高い未来):インフラ整備や新型車投入が計画通りに進み、2030年のBEV新車販売シェアは5%〜8%程度に。街でBEVを見かける機会は増えるが、依然としてハイブリッド車が主流。
- 上振れシナリオ(うまくいけば…の未来):集合住宅の充電問題が画期的に解決され、国産メーカーから大ヒットする手頃なBEVが登場した場合、シェアは10%を超え、普及に弾みがつく。
- 下振れシナリオ(最悪の場合…の未来):補助金の急な打ち切りやインフラ整備の遅れ、円安による車両価格の高止まりなどが重なると、シェアは5%未満に留まり、普及は停滞する。
▼焦る必要はない、でもアンテナは張っておこう
車選択メモとしては、「今すぐ誰もがBEVに乗り換えるべき」とは考えていません。あなたの生活スタイルや住環境によっては、まだハイブリッド車やガソリン車の方が合理的な選択である場合も多いでしょう。
しかし、BEVを取り巻く環境が凄いスピードで変化していることも事実です。技術は日進月歩で進化し、今日「無理だ」と思っていることが、2〜3年後には当たり前になっているかもしれません。大切なのは、焦って結論を出すことではなく、常に最新の情報にアンテナを張り、「自分にとっての最適な買い替えタイミング」を見極めることではないでしょうか。
▼変化の主役は「あなた」かもしれない
最終的にBEVを普及させるのは、政府の目標やメーカーの戦略だけではありません。新しい技術にワクワクし、環境への貢献を考え、勇気を持って最初の一歩を踏み出すユーザー一人ひとりの選択です。次に日本のBEVの歴史を動かすのは、この記事を読んでいるあなたかもしれませんね。
「bZ4Xは売れない?」記事まとめ
- トヨタ bZ4Xの販売不振は、単一の原因ではなく、価格、販売戦略、品質問題、そして商品力という複数の課題が複合的に絡み合った結果です。
- 国の補助金を活用しても、テスラやヒョンデといった競合EVと比較して「高すぎる」価格設定が、消費者の購入意欲を削ぐ最大の要因となりました。
- 当初、個人向けにはサブスクリプションサービス「KINTO」限定という特殊な販売方法をとったことで、現金購入を望む多くの潜在顧客を逃す結果につながりました。
- 発売直後に発生したホイール脱落の危険性に伴う大規模リコールが、製品への信頼性とブランドイメージを大きく毀損しました。
- 航続距離や充電性能、内装の質感など、スペック面でライバルを圧倒するような明確な強みや魅力を打ち出せなかったことも、厳しい評価の一因となっています。
- 以下、参考出典
- トヨタ自動車(bZ4X)