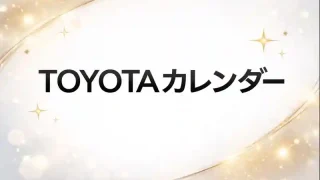「トヨタ ミライは売れない」——そんな声を聞いて、「やっぱり水素の燃料は厳しい?」そう思ったことはありませんか?
最先端の燃料電池を搭載し、走行中に排出するのは水だけ。環境に優しい究極のエコカーとして華々しく登場したトヨタのミライ。しかし、街で頻繁に見かけるかと言われると、少し首をかしげてしまうのが正直なところかもしれません。
この記事では、専門家ではないけれど誠実な情報収集を心がける筆者が、あなたに代わって「ミライが売れない」と言われる背景を徹底的に調査しました。難しい専門用語は使わず、数字や事実をもとに、一つひとつ丁寧に解説していきます。
この記事を読めば、以下の点が分かります。
- どれくらい売れていない?【最新の販売台数】
- なぜ売れないの?【3つの大きな理由】
- 水素ステーションは今後増えるの?【増設計画の現実】
- そもそも誰が買っているの?【意外なユーザー層】
トヨタ ミライは売れない?【販売台数】早見表
トヨタ ミライの販売台数は、2021年に一時的なピークを迎えた後、特に国内市場で大きく落ち込んでいるのが現状です。数字を詳しく見ていくと、話題性とは裏腹に、継続して売れ続けることの難しさが浮き彫りになります。ここでは、日本とアメリカの市場を中心に、ミライがどれくらい売れてきたのかを具体的なデータで見ていきましょう。
【販売台数】売れない現状をデータで確認
まずは、ミライの販売台数がどのように推移してきたのか、下の表で確認してみましょう。
トヨタ ミライ 販売台数の推移(日本・米国)
| 年 | 日本(台) | 米国(台) |
|---|---|---|
| 2014 | 7 | – |
| 2015 | 411 | 72 |
| 2016 | 950 | 1,034 |
| 2017 | 766 | 1,838 |
| 2018 | 575 | 1,689 |
| 2019 | 644 | 1,502 |
| 2020 | 717 | 499 |
| 2021 | 2,438 | 2,629 |
| 2022 | 831 | 2,094 |
| 2023 | 318 | 2,737 |
| 2024 | 97 | 499 |
| 2025* | 50(1–7月) | 157(YTD) |
(※:JADA集計。日本は登録台数、米国は販売台数ベース。)
こうして見ると、日本では2代目モデルが登場した2021年に2,438台と販売が大きく伸びましたが、その後は急激に減少していることが分かります。
2024年には、年間でわずか97台という数字に。未来の車として華々しくデビューしましたが、今は少し寂しい状況と言えるかもしれません。
一方、アメリカでは2023年に一度持ち直したものの、2024年に入ってからは再び販売が落ち込んでいます。
世界全体での販売状況も失速気味
トヨタの公式発表によると、ミライは2014年の発売以来、世界全体で約2.8万台(2025年時点)が販売されたとのことです。
ただ、最近の報道では2024年の年間販売台数は世界で2,000台に満たない見込みとも言われており、世界的に見ても苦戦している様子がうかがえますね。
▼なぜ販売台数が伸び悩むのか?
この数字の裏には、単純な車の性能だけではない、もっと根深い理由が隠されていそうです。例えば、燃料である水素を補給するインフラの問題や、燃料そのものの価格など、ユーザーが日常的に使う上でのハードルが影響しているのかもしれません。次の章で、その「売れない理由」を詳しく見ていきましょう。
トヨタ ミライが売れない3つの理由
トヨタ ミライが販売に苦戦している背景には、大きく分けて「インフラ」「コスト」「市場」という3つの構造的な課題が存在します。どれだけ車の性能が優れていても、ユーザーが安心して快適に使える環境が整っていなければ、購入の選択肢に上がりにくいのが現実です。ここでは、その3つの理由を一つずつ掘り下げていきます。
理由①:水素ステーションが少なすぎる問題
ミライにとって最大のアキレス腱ともいえるのが、水素ステーションの問題です。
ガソリンスタンドのようにどこにでもあるわけではなく、数自体が限られています。日本では2024年末時点で全国に約160ヶ所(2023年は166で減少した)と、まだまだ少ないのが現状です。
さらに深刻なのは、その「不安定さ」です。アメリカのカリフォルニア州では、大手企業であるシェルが乗用車向けの水素ステーション事業から全面撤退するという出来事がありました。
また、開いているはずのステーションがメンテナンスなどで「長期停止」しているケースも少なくありません。「今日、あそこのステーションは使えるだろうか?」と、当日になるまで分からないような状況では、毎日の通勤や休日のドライブに使うのは少し勇気がいりますよね。
理由②:「価格」と「補助金」頼みの実情
2つ目の理由は、シンプルにお金の問題です。ミライは、購入時の車両価格も、購入後の燃料代も、他の車と比べて割高になる傾向があります。
まず水素の価格ですが、2024年には日本でもアメリカでも大幅な値上げがありました。日本では、大手事業者Iwataniが1kgあたり1,210円から1,650円に値上げした例もあります。
車両価格も、決して安くはありません。ミライの新型MIRAI発売時の価格は710万円から805万円で、2024年時の購入には国の補助金(最大255万円)が頼りになりました。
しかし、補助金があったとしても、日々の燃料費の高さを考えると、ハイブリッド車や電気自動車(BEV)と比べて総コストで不利になる可能性があります。
さらに、中古車市場での価値が下がりやすいという指摘もあり、手放すときのことまで考えると、経済的な負担は小さくないかもしれません。
理由③:乗用FCV市場そのものが縮小
最後に、ミライを取り巻く自動車市場全体の変化が挙げられます。
かつてはホンダも「クラリティ」という燃料電池自動車(FCV)を販売していましたが、2021年に生産を終了しました。韓国のヒョンデも「ネッソ」というFCVを出していますが、次期モデルの開発は遅れているとの報道もあります。
つまり、乗用車としてのFCV市場そのものが、世界的に縮小している雰囲気があるのです。
当のトヨタ自身も、最近ではFCシステムの主戦場を乗用車からトラックやバスといった「商用車」へ移す姿勢を鮮明にしています。商用車は走行ルートや燃料補給の場所が固定されているため、FCシステムとの相性が良いんですね。
こうなると、乗用車であるミライのためのインフラ整備や開発の優先順位は、どうしても下がってしまう可能性があります。
▼結局のところ…
ミライが売れない理由は、車そのものの魅力というよりは、それを取り巻く環境、つまり「安心して乗れる土台」がまだ整っていない点に集約されると言えそうです。インフラの不安、コストの高さ、そして市場の縮小。この三重苦が、ミライの普及を阻む大きな壁となっているのかもしれませんね。
水素ステーションって増設計画どうなってるの?
水素ステーションの増設計画は、日本の公式目標では2030年度までに約1,000ヶ所とされていますが、2024年末時点で約161ヶ所という実績を見ると、その進捗は大幅に遅れているのが実情です。さらに、最近の政策は乗用車向けよりもトラックやバスといった商用車を重視する方向へシフトしており、私たちの身近な場所にステーションが増えるペースは、期待よりも緩やかになる可能性が高いでしょう。
【日本の現状】水素ステーション計画の遅れ
政府が掲げる目標はとても壮大です。
- 2025年までの中期目標:320ヶ所
- 2030年度までの最終目標:約1,000ヶ所
しかし、現実の数字を見てみると、2024年末時点での稼働数は161ヶ所。この1年間で新しくできたのは8ヶ所でしたが、閉鎖などもあったため、全体の数としてはわずかに減っています。
今のペース(年間8ヶ所増)のままだと、2030年度の目標達成はかなり厳しい道のりです。目標を達成するには、これから毎年140〜170ヶ所という、今とは比べ物にならないペースで増やしていく必要があります。
【なぜ?】商用車優先へと方針転換
なぜ計画が進まないのでしょうか。その背景には、政府の方針転換も見え隠れします。
最近の国の水素基本戦略では、乗用車だけでなくトラックやバスなど、様々な乗り物が使える大規模なステーションを重視する姿勢が示されています。
これは、決まったルートを走る商用車の方が、ステーションの採算を取りやすいという判断があるからでしょう。乗用車ユーザーにとっては、少し寂しい方針転換かもしれません。
【今後】海外と比べた日本の将来性
世界に目を向けても、日本のペースは少しゆっくりに見えます。
2024年に新設された水素ステーションの数は、世界全体で約125ヶ所。その内訳は、欧州が42ヶ所、中国が約30ヶ所、韓国が25ヶ所となっており、日本の8ヶ所と比べると、その差は明らかです。
特にFCVの普及が進んでいたアメリカのカリフォルニア州でも、乗用車向けのステーションは増えておらず、むしろ閉鎖や長期停止が問題になっています。
▼地図上の「点」より「使えるか」が重要
私たちドライバーにとって大切なのは、地図アプリに表示されるステーションの数よりも、「今日、今から、確実に使えるステーションがあるか」ということですよね。計画の数字はあくまで目標。実際にミライのようなFCVがストレスなく走り回れるようになるには、数の増加だけでなく、いつでも安心して使えるという信頼性の向上が不可欠と言えそうです。
トヨタ ミライってどういう人が買ってるの?
トヨタ ミライのオーナーは、実は個人よりも官公庁や企業といった「組織」が中心です。発売当初の日本では受注の約6割が法人だったというデータもあり、環境対策のアピールや実証実験といった明確な目的を持って導入されるケースが目立ちます。個人ユーザーもいますが、その多くは水素ステーションが近くにあるなど、限られた条件を満たせる方々のようです。
意外なオーナー像①:官公庁やタクシー会社
ミライのユーザー像を紐解くと、いくつかのパターンが見えてきます。
- 官公庁・自治体の公用車
国の省庁や市役所などが、脱炭素社会への取り組みをアピールする「走る広告塔」として導入するケースです。首相官邸に納車されたことも、その象徴的な出来事でした。 - タクシー・ハイヤー
ミライの静かでクリーンな乗り心地は、お客様をもてなすタクシーやハイヤーにぴったりです。走行ルートがある程度決まっているため、水素ステーションの場所さえ押さえておけば運用しやすいというメリットもあります。 - 企業のフリート(社用車)
環境への配慮(ESG経営)を重視する企業が、社用車として導入する例です。また、国際オリンピック委員会(IOC)の公用車として使われるなど、世界的なイベントでその姿を見ることもあります。
意外なオーナー像②:補助金狙いの個人
もちろん、個人でミライを所有している方もいます。特にアメリカのカリフォルニア州では、個人ユーザー向けの強力なインセンティブが用意されていました。
例えば、
- メーカー施策として最大15,000ドル(約200万円以上)相当の水素燃料が無料(地域・期間・条件あり)
- 複数人乗車レーン(HOVレーン)を1人でも走行可能(2025年10月終了)
- 大幅な車両価格の値引き
といった特典です。
ただし、これらの特典があったとしても、自宅や職場のすぐ近くに「確実に稼働している」水素ステーションがあることが、購入の絶対条件になりやすいようです。インフラの不安定さから、満足度は人によって大きく左右されるという現実もあります。
▼「使いどころ」がハマる層に選ばれる車
こうして見ると、ミライは「誰でも気軽に買える車」というよりは、「特定の利用シーンや目的に合致する層」に選ばれている車だということが分かります。組織にとっては環境への姿勢を示すシンボルとして、一部の個人にとってはインセンティブと生活圏が噛み合った賢い選択として、その価値を発揮しているのかもしれませんね。
FCV(燃料電池自動車)は今後どうなるのか?
FCV(燃料電池自動車)の未来は、乗用車での爆発的な普及というよりは、トラックやバスといった「商用車」が主戦場になっていく可能性が高いでしょう。エネルギー効率の点では電気自動車(BEV)に軍配が上がりますが、長距離輸送や短い時間でエネルギーを充填する必要がある領域ではFCVに強みがあるため、今後はそれぞれの得意分野で役割分担が進んでいくと考えられます。
【今後の展望】主戦場はトラック・バスへ
これからのFCVを考える上で重要なのが、「乗用」と「商用」の分岐です。
乗用FCVは、残念ながら当面はニッチな存在であり続ける可能性が高いです。その理由は、エネルギー効率でBEVに劣ること、そして個人向けに水素ステーション網をくまなく整備するのが非常に難しいからです。
一方で商用FCV、特に長距離トラックやバスの分野では、大きな期待が寄せられています。
- 短い充填時間: ガソリン車並みの時間でエネルギーを充填できるため、稼働率を下げたくない商用車には好都合です。
- 長距離走行: 一度の充填で長い距離を走れるため、都市間を結ぶトラックなどに適しています。
- インフラの効率性: 高速道路の幹線沿いや物流拠点など、決まった場所にステーションを集中配置すれば良いため、投資効率が高いのです。
世界の潮流:商用車を後押しする政策
各国の政策も、商用FCVの普及を後押しする流れになっています。
ヨーロッパ(EU)では、2040年までに大型トラックのCO2排出量を90%削減するという厳しい規制を導入。同時に、主要な高速道路(TEN-Tコアネットワーク上)に200kmごとに水素ステーションを設置することを義務付けています。
日本でも、水素社会推進法という新しい法律が作られ、水素を使いやすくするための価格差補助(CfD)といった支援策が始まります。これも、主に商用分野での利用を後押しするものです。
【未来】技術革新で価格は下がる?
もちろん、FCVの技術が止まっているわけではありません。
トヨタは、より低コストで耐久性が高く、航続距離も伸びる第3世代のFCシステムを開発しており、2026年以降に商用車を中心に投入していくと発表しています。
技術の進化によってFCVの性能や経済性が向上すれば、未来の選択肢としてさらに魅力的な存在になっていくでしょう。
▼未来のシナリオ
FCVの未来を想像すると、「一家に一台」という姿よりは、私たちの生活を支える物流トラックや公共バスとして、街中で活躍する姿が目に浮かびます。乗用車は「好きだから乗る」という趣味性の高い領域に、商用車は「仕事道具として優れているから選ぶ」という実用性の領域に、それぞれ進化していくのかもしれません。BEVとFCVが、お互いの長所を活かして共存する未来が、すぐそこまで来ていると言えそうです。